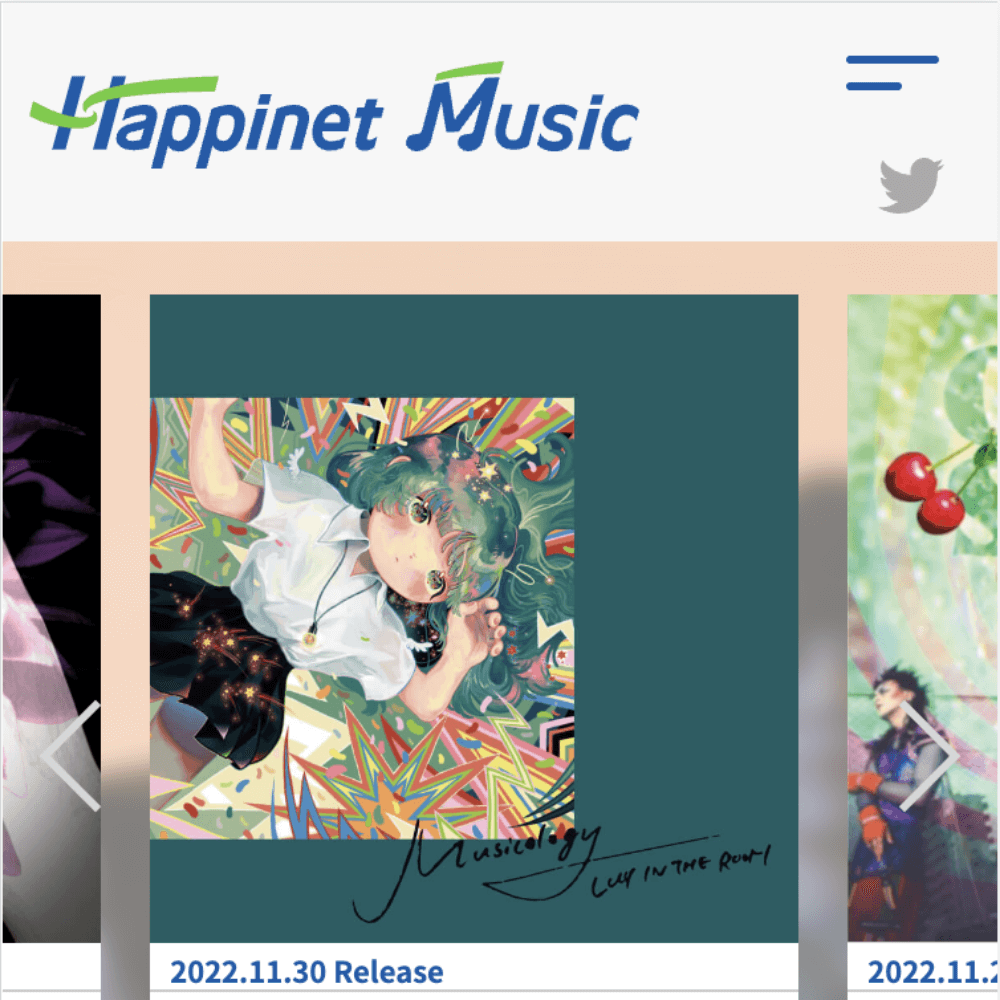Gerbera Music Agency
We're Gerbera Music Agency
Music empowers all life
すべての人に、音楽の魅力を届ける
About
私たちの特徴
アーティストの自己実現に貢献する
音楽業界特化型
デジタル広告エージェンシー
「新しい音楽を好きになるきっかけ」を生み出すために、マーケティングプラン、クリエイティブ、体験設計を考え抜き、デジタル広告をはじめとした様々なサービスを提供します。
→ 特徴を見るService
デジタル広告
新たな接点をつくり、
継続的な活動を
支えるファンベースを生み出す
音楽愛に基づくプランニングを元に、アーティストの新しいファンが増える広告配信を実現。ファンベース成長によるストリーミング再生増加は、アーティスト活動を支える収益還元に繋がります。
→ サービスを見るWorks
ご支援事例
100社、1,000楽曲を超える広告を配信。
契約継続率は80%以上。
日々蓄積される、音楽業界に特化した広告運用の知見。最先端のアドテクノロジーを駆使して、限られたご予算の中で最大の広告成果を目指します。
Blog
ブログ
スタッフによる広告運用ブログや、市場トレンド、マーケティング、ブランディングなどに関する記事を更新しています。
-
 お客さまインタビュー| 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメントさま
お客さまインタビュー| 株式会社JVCケンウッド・ビクターエンタテインメントさま#インタビュー #ご利用事例 #マーケティング
-
 音楽広告の遷移先論争〜YouTube直飛ばし vs スマートリンク〜
音楽広告の遷移先論争〜YouTube直飛ばし vs スマートリンク〜#Instagram広告 #Spotify #TikTok広告 #マーケティング #広告知識
-
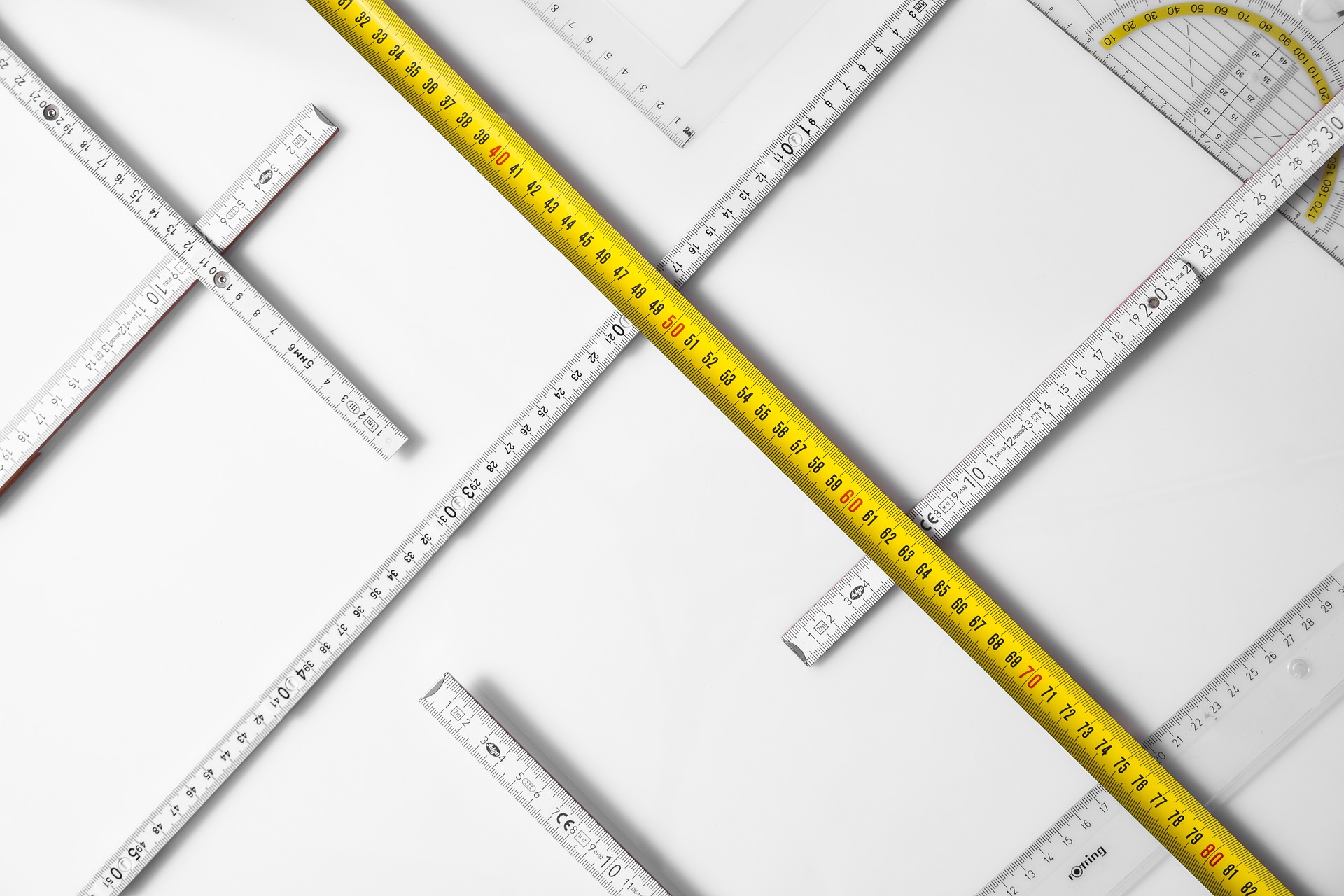 ストリーミングヒットを生むために必要な取り組みと、当社が寄与できること
ストリーミングヒットを生むために必要な取り組みと、当社が寄与できること#Instagram広告 #TikTok広告 #マーケティング #広告知識 #音楽シーン
News
ニュース
メディア掲載やイベント参加など、Gerbera Music Agencyのニュースをお知らせします。
-

-

-
 音楽業界のアーティストに特化したTikTok運用プランを低価格で提供開始
音楽業界のアーティストに特化したTikTok運用プランを低価格で提供開始2024.03.07
For Brand
ブランドの方へ
音楽をきっかけとして
メッセージを届けることができます

私たちは、音楽愛に基づく企画力と、音楽業界との信頼ある繋がりを元に、音楽を通してブランドと生活者の新しい接点をつくるプロジェクトをサポートしています。Spotifyでのブランドプレイリスト制作数は日本一。その他ポッドキャストやキャスティングなどブランドの音楽企画も多数実績がございます。非公開実績は資料で紹介しているため、お気軽にお問い合わせください。一緒に音楽プロジェクトを始めましょう!
→ ブランド向けサービスを見るRecommend Music
おすすめ音楽
GMAが運営するプレイリストメディア『Pluto』セレクターが今おすすめ音楽をプレイリスト『Pluto Selection』を隔週更新中!
また、セレクターがプレイリストの裏側をゆるく話すポッドキャスト『Pluto radio』も日々更新中!ぜひチェックしてみてください。